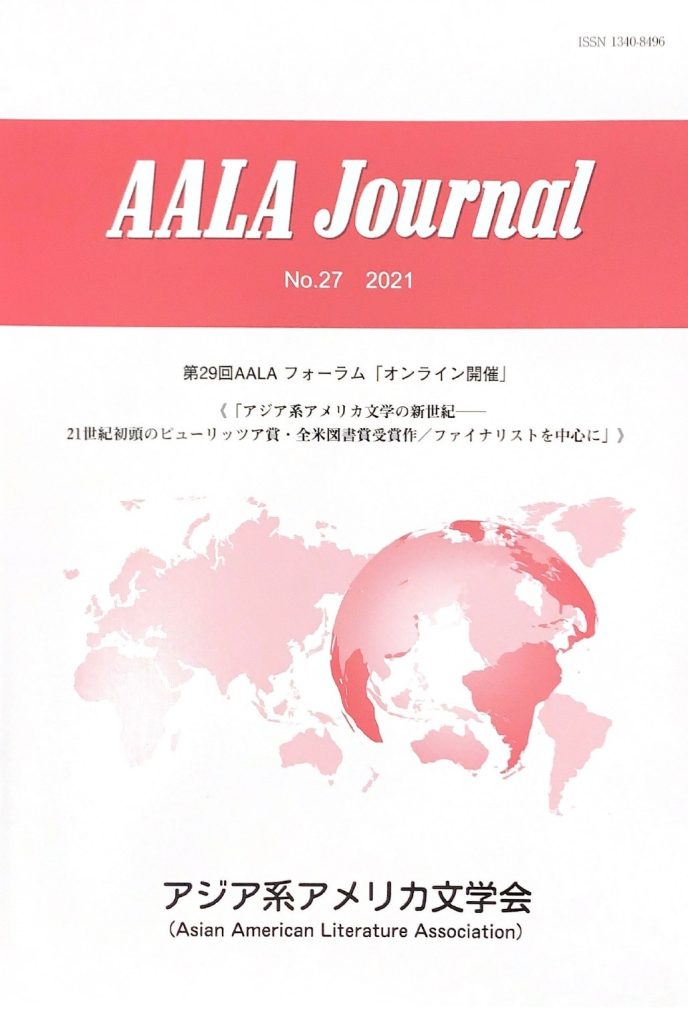第30回AALAフォーラム (AALA Forum 2022) プログラム
「アジア系アメリカ文学研究とトランスボーダー性/オリエンタリズム――村上春樹と小野姉妹を中心に」
<フォーラム趣旨説明>
これまでアジア系アメリカ文学研究は様々な理論・方法論を取り入れることによって発展してきたが、そうした理論・方法論を従来の研究対象(狭義の「アジア系アメリカ文学」)から広げて適用することは可能であろう。今回のフォーラムでは、アジア系アメリカ文学研究の中で培われてきた「トランスボーダー性」や「オリエンタリズム」というパースペクティヴに拠って、村上春樹と小野姉妹という日本を代表して世界的に活躍する作家・アーティストについて考察したい。ひいては、この試みによってアジア系アメリカ文学研究の枠組を拡大し、研究内容を深化させることを目指している。(山本秀行)
日時:2022年9月25日(日)9:50~16:10
会場:早稲田大学早稲田キャンパス11号館4階第4会議室
*当日キャンパス内には案内板等のご用意はございません。正門・南門等より11番の校舎までお進みください。
キャンパスマップ
9:30 ~ 9:50 受付
9:50 ~ 10:00 開会の辞 山本秀行(AALA会長:神戸大学)
10:00 ~ 12:00
講演「副業としての翻訳家: 村上春樹から始まった20年を振り返って」
講師:辛島デイヴィッド(早稲田大学)
司会:麻生享志(早稲田大学)
ミニ・シンポジウム「トランスボーダー文学としての村上春樹」
発表者:仁平千香子(山口大学)
山本秀行(神戸大学)
12:00 ~ 13:00 昼休み(*下記注意事項をご確認ください。)
13:00 ~ 13:30 総会
13:30 ~ 16:00
シンポジウム「アジア系アメリカ文学とオリエンタリズム――小野姉妹の功績を中心に」
司会・講師:牧野理英(日本大学)
講師:田ノ口誠悟(日本学術振興会特別研究員PD)、矢口裕子(新潟国際情報大学)、松川祐子(成城大学)
16:00 ~ 16:10 閉会の辞
* 感染症対策から、構内でのマスクの着用をお願いいたします。また、会場での飲食は、水分の補給のみでお願いいたします。当日キャンパスではご昼食等の提供はございません。各自ご用意いただき、キャンパス内の認められた場所での黙食をお願いいたします。
[登壇者プロフィール・発表概要等]
講演「副業としての翻訳家: 村上春樹から始まった20年を振り返って」
[講演者紹介] 辛島 デイヴィッド(David Karashima)先生
1979年東京都生まれ。作家・翻訳家。現在、早稲田大学国際教養学部准教授。タフツ大学(米)で学士号(国際関係)、ミドルセックス大学(英)で修士号(文芸創作)、ロビラ・イ・ビルヒリ大学(西)で博士号(翻訳・異文化学)取得。日本文学の英訳や国際的な出版・文芸交流プロジェクトに幅広く携わる。2016年4月から2017年3月まで、NHKラジオ「英語で読む村上春樹」講師もつとめた。主な著作として、『Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んでいる者たち』(みすず書房、2018)、『文芸ピープル―「好き」を仕事にする人々』(講談社、2021)、「インターセクションズ」(『すばる』2022年5月号掲載)などがある。
ミニ・シンポジウム「トランスボーダー文学としての村上春樹」
[ミニ・シンポジウム概要]
本ミニ・シンポジウムでは、村上春樹研究の著書や論文を出版されている辛島デイヴィッド先生を囲んで、2名の発表者(山本および仁平先生)が「トランスボーダー文学としての村上春樹」という観点から、それぞれの観点・テーマから発表を行う。その後辛島先生からコメントや質問をいただいた後、フロアの会員の方々も交え、ラウンドテーブル・ディスカッションを行う。村上春樹の母校であり、また、2021年10月に国際文学館(村上春樹ライブラリー)が開館したことが話題になった早稲田大学において開催される本ミニ・シンポジウムで、「トランスボーダー文学としての村上春樹」という新たな姿を浮かびあがらせることができたら幸いである。(山本秀行)
[ミニ・シンポジウム 発表要旨]
1. 「国境を越えた共感:村上春樹の国際的人気の理由を考える」 仁平千香子(山口大学)
村上春樹は国内外で多くの読者を獲得してきたが、国内の文学研究者や文芸評論家からの意見はデビュー当時から変わらず厳しい。ファンタジー要素が強いことや日本の社会問題や歴史に直接切り込まないスタイルは、逃避的と批判されたり、作者の日本人としての意識の希薄さと判断されたりしてきた。これらの批判的意見の背後には、「理想的な(純)文学のあり方」というある種の定型が固定化され共有されていると考えられるが、一方で読者の根強い人気は否定できるものではなく、また見過ごすべきでもない。また日本文学の海外受容に関して言えば、谷崎や三島、川端の読者はいわゆる「伝統的日本」を求めてこれらの作品を読む傾向があったのに対し、村上の読者は日本について知ろうと村上作品を読むことはない。そこには文化的差異を越えた共感があり、それが読者とある種の化学反応を起こしていると考える方が自然である。本発表では、文化的特殊性や時代的特殊性を越えて読者に訴える村上作品の特徴について考えたい。
2.「村上春樹「ドライブ・マイ・カー」とその映画版におけるインターテクスト的トランスボーダー性」 山本秀行(神戸大学)
濱口竜介監督の映画『ドライブ・マイ・カー』(2021)は、2021年度アカデミー賞国際長編映画賞を受賞するなど、世界的高評価を受けた。原作である村上春樹の同名の短編(2013年初出)のタイトルはThe Beatlesの曲‟Drive My Car”(1965)に由来し、主人公の名前の家福(Kafuku)は2002年の小説『海辺のカフカ』の主人公の名前、あるいはその由来となっているFranz Kafukaを想起させるなど、他作品とのインターテクスト性によって、本作品のトランスボーダー性が補強されている。妻を亡くしたベテラン俳優の主人公家福が、愛車Saabの運転手として雇った無口で影のある若い女性みさきとの交流を通して人生の意味を模索するというメイン・プロットに、アントン・チェーホフの戯曲『ワーニャ伯父さん』の韓国人製作者による多言語上演に主人公が監督(兼俳優)として関わり成功させるというインターテクスト的サブ・プロットが加わった映画版では、世界的アピール力を備えたトランスボーダー性がより顕著である。本発表では、こうした原作短編と映画版におけるインターテクスト的トランスボーダー性について詳細に検討したい。
シンポジウム「アジア系アメリカ文学とオリエンタリズム――小野姉妹の功績を中心に」
[シンポジウム概要]
本シンポジウムの主旨は、第二次世界大戦前後に日本に生まれ、その後国家的概念から大きく逸脱して世界をかけめぐることになる小野姉妹―オノ・ヨーコ、そして小野節子―の60年代、70年代の功績に着目し、彼らのオリエンタリズムに対する視点がいかにアジア系アメリカという領域を再定義していたのかという問題を議論するというものである。
オノ・ヨーコとは、反戦運動や、Nutopia設立といったトランスボーダーな平和主義を前面に掲げ、常に英米社会を挑発し続けた日本出身の前衛芸術家である。1969年にジョン・レノンとセンセーショナルな形で結婚式を挙げたことから、ともすれば「レノンの妻」という立ち位置ばかりが注目されがちであるが、実際には日本にいた頃から、斬新な芸術的手法と大胆なる行動力をもって活動し続けた人物である。ちなみに日系アメリカ作家カレン・テイ・ヤマシタは最新作『三世と多感(Sansei and Sensibility)』(2020)所収の短編「ボルヘスとわたし(“Borges and I”)」において、オノ・ヨーコとレノンの相互的かつ対等なる関係性を描いている。
一方小野節子という名前からオノ・ヨーコの妹という血縁関係を見出すことのできる人間はいないだろう。この人物の背景を見てみると、そこには太平洋戦争とともに生まれ、その後芸術と経済といった相異なる分野を極め、全世界を駆け巡った類まれなる国際人の姿をみることができるからだ。その人生には芸術家と起業家の接点ともいえるダイナミックな創造力が顕在化されている。70年代にスイスのジュネーブ大学大学院で執筆した博士論文には、オリエンタリズムという概念に正面から切り込み、そこから新たな視点を見出していた小野の慧眼が伺える。
本シンポジウムでは、田ノ口氏、矢口氏、そして松川氏の論考をベースに、オノ・ヨーコと小野節子の類稀なる才能が、オリエンタリズムというテーマを軸にどのように展開していったのかを分析していきたい。(牧野理英)
[シンポジウム発表要旨]
1.「小野節子とラフカディオ・ハーン」 牧野理英(日本大学)
小野節子の人生とその博士論文が示すのは、オリエンタリズムという概念に対し真正面から取り組んだ日本人の研究者としての姿勢である。1941年、銀行家の小野英輔・磯子夫妻の次女として東京に生まれ、両親とともに5年間アメリカで生活したのち、60年代後半にはスイス・ジュネーブ大学付属高等国際問題研究大学院比較文学科に入学した小野は、72年にはこの博論を書き終える。この40年代生まれで70年代に活動を始める日本人の姿に筆者が注目している理由とは、激動の日本と共に生き、その国家性を国内のみではなくトランスナショナルな視点からとらえ、世界に発信するといった離れ業を70年代にスイスでやってのけたという点にあるだろう。国民意識に関して、そこで生まれ育った民族が特権をもって語るという形式に終始していたアメリカのエスニック文学が公民権運動から70年代にかけて注目されていた時代に、それをはるかに超越した形で、日本が欧米でどのように見られていたのかを逆の視点から追求していたのが小野節子であった。
ピエール・ロティ(Pierre Loti)とラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn)の展開する日本論とは、それぞれ現代では日本研究およびオリエンタリズム研究において重要な文献であることはいうまでもないが、70年代初頭にこれを比較し、両作家の視点の限界を指摘することで、徳川政権の徳川慶喜の体現する姿に新しい日本人像を見出したのはおそらくこの小野がはじめであったと思われる。ここではこの博士論文を概観すると共に、筆者がこの論文を翻訳する上で感じた感想も交えながら、このエドワード・サイード(Edward Said)に先んじる小野のオリエンタリズム再考を、ラフカディオ・ハーンを起点に試みたいと思う。
2.「小野節子とピエール・ロティ」 田ノ口誠悟(日本学術振興会特別研究員PD)
ピエール・ロティ(Pierre Loti, 1850-1923)は近代フランスの小説家、海軍士官であり、オペラ『蝶々夫人』の原作ともなった『お菊さん』(1887)など、自身の航海における異国の人々との交流をもとにした異国趣味的・エキゾティックな作品で広く知られている。しかしフランス文学においては、彼の作品はどちらかというと見聞録、旅行記に類するものとして扱われがちであり、その文学作品としての特色を真正面から考察する研究は多くないと言える。この点で、小野節子が1972年にジュネーブ大学大学院比較文学科に提出した博士論文『日本に対する西洋のイメージ:ロティとハーンを通して西洋人は何を見たのか』の意義は極めて大きかった。小野はそこで、『お菊さん』を始めとするロティの日本を主題とした作品を分析し、それらが「イメージ」という能動的な想像/創造の営為の所産であったことを示しているのである。本発表では、小野の分析を整理しつつ、その上でロティ作『お菊さん』を読解し、その独自のイメージの文学としての特性を明らかにする。その中で、ロティ作品の文学史的意義はもちろん、近年の文学研究においては単純な文化的偏見の具現として敬遠されがちな異国趣味文学やオリエンタリズム的作品を再評価する道筋も見えてくるだろう。
3.「オノ・ヨーコのオリエンタリスト/フェミニスト・パフォーマンス」 矢口裕子(新潟国際大学)
パフォーマンス・アーティストとしてのオノ・ヨーコの出発点を、仮に1955年の Lighting Pieceに置くなら、そのちょうど60年後の2015年、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で行われた個展、Yoko Ono: One Woman Show, 1960-71が初期作品を集中的に取りあげたのは、故なきことではない。第一に、それがまさに1971年、MoMAを想像上の会場として開催された架空の展覧会、One Woman Showへの、MoMAからの44年後の応答であったこと、第二に、何よりもまずジョン・レノン夫人としてオノを認識する世界に対して、レノン以前の前衛アーティスト、オノを提示すること、第三に、21世紀時点から見ても、初期作品にこそオノの可能性の中心があると考えられるためではないか。
本発表では、玉虫厨子の捨身飼虎図にインスピレーションを受けたとされる、オノの代表的パフォーマンス作品Cut Piece (1964)を、オリエンタリズムとフェミニズムの交差路に立ちあがるものと捉え、フランス人アーティスト、ニキ・ド・サンファルのShooting(1961)と比較するとともに、3/11以降バトラーが展開する新しい肉体の存在論、抵抗としての被傷性の議論に接続する。さらに、2021年、ディズニー+で配信が開始された、解散間際のビートルズのドキュメンタリー映像Get Backに映しだされるオノの姿を、無作為の作為、沈黙のノイズ、可視と不可視のあわいを揺れ動く抵抗のパフォーマンスと捉え、それがある幼い娘を「叫ぶ少女」に変容させるまでを追う。
4.「パリンプセストとしてのThe Yoko Ono Project」 松川祐子(成城大学)
アジア系北アメリカの文学と文化におけるオノ・ヨーコの影響力は計り知れないが、オノ・ヨーコが女性として、そして芸術家として、登場人物たちに大きな刺激を与えるアジア系北アメリカ文学作品をひとつ挙げるなら、韓国系劇作家ジーン・ユン(Jean Yoon, 1962- )のThe Yoko Ono Project(2000)を選びたい。カナダを拠点に女優としても活躍するユンは、この作品にオノ・ヨーコ自身の作品を多数組み込み、マルチメディア戯曲として完成せた。オノ・ヨーコの展覧会で出会う主人公のアジア系女性たち3人は、いくつものオノ作品を体験しながらアジア系北アメリカ人女性としてのアイデンティティとオノ・ヨーコとの複雑な関係について語り始める。
本発表では、The Yoko Ono Projectでのオノ作品、オノ作品を体験する主人公たちとキャスト、主人公たちの追体験をしながら芝居に参加する観客、そしてThe Yoko Ono Project全体を鑑賞する観客や読者からなるパリンプセスト的重層性に着目する。可視化されたこれらの層でユンがオノの作品に重ねる現代アジア系北アメリカのコンテクストを通して、オノの先駆的ヴィジョンとユンの描くアジア系女性像と現代社会批判について探る。
参加申込方法および問合せ先 ※「アットマーク」はすべて半角の@にご変換ください。
- 参加される方は、2022年9月16日(金)までに電子メールで必要事項(ご氏名、ご所属、ご連絡先等)を明記の上、事務局・深井(fukaiアットマークsuma.kobe-wu.ac.jp)までお申し込みください。
Google Formからもお申し込み可能です。https://forms.gle/y8nmox7HoscD6xAd8 - 非学会員の方も参加できます。
- ご宿泊先については、各自でお申し込みください。なお、この時期は観光等で各施設の混雑が予想されることから、早めのご予約をおすすめいたします。
- お問い合わせは、開催校担当者麻生まで電子メール(asoesアットマークwaseda.jp)にて、その他については学会事務局(hdyamamoアットマークlit.kobe-u.ac.jp)までご連絡ください。